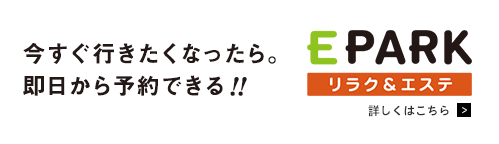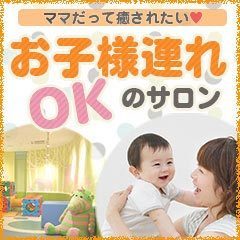2016年1月27日 更新
【肩こりレッスン3】その予防と対処法について

【肩コリスト必見!】肩こりは予防できる
ヒトを含む動物は、本来“動くもの”であり、筋肉は動かさないと衰えるか固まるといいます。子供がじっとしていられないのはある意味で自然な姿であり、便利な道具がたくさんできてヒトが動かなくなってから、肩こりはぐっと増えてきました。
また、肩こりレッスン2でお伝えしたように、背中を丸めるなどの悪い姿勢も肩こりの大きな原因だと考えられています。これらを裏返せば、『こまめにカラダを動かす』『正しい姿勢をとる』ということを心がけるだけでも、かなり有効な肩こり予防になるといえます。
では、具体的にどんなことをすればいいか? 厚生労働省が『VDT作業※における労働衛生管理のためのガイドライン』で推奨しているのが、「連続作業が1時間を超えないようにし、途中で1~2回程度の小休止を入れる」こと。
このとき、肩を回したり上下させたり、ストレッチをするなどして、こわばりがちな肩まわりの筋肉を動かすことで肩こりの予防ができます。また、デスクワークを続けていると、どうしても前傾姿勢になってくる。すると、花がしおれるように重たい頭がどんどん前へと落ちてきます。これを支えるために、首・肩・背中の筋肉は緊張を強いられ、やがて“肩こりスパイラル”の幕が上がることに…。
これを回避させるのが、“正しい姿勢”です。椅子に座るときは深く腰掛け、背骨の上に頭をバランスよく載せる気持ちで。アゴを引き、背中を丸めないよう意識してみてください。そもそも、傾いた頭を肩の筋肉で支えようとするから肩こりになるのであり、頭を背骨で支える、つまり“けん玉”のように、中心軸に対して球体がすっと垂直に載っかっていれば、筋肉への負担を最小限に抑えることができるのです。
なお、意外と見逃しがちですが、高すぎる枕やサイズの合わない服も、知らないうちに肩に負担をかけてしまうとか。寝具や服装にも気を配れば、より効果的に肩こりを予防することができるでしょう。
※VDT作業=ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業。(厚生労働省HPより)

「動いて、ほぐして、温めて」。今すぐ“こり”に負けないカラダを作ろう!
「でもやっぱり肩こりが気になる」「バリバリの肩を、すぐに何とかしたい!」というときは、こんな対処法がおすすめです。
もっとも手っ取り早いのが、「温める」こと。筋肉は、寒いと熱を逃がさないように収縮し、あたたかいとゆるむという性質をもちます。この原理を活用し、こわばった筋肉を温めてゆるめることで、血液循環をよくして肩こりを改善させるという作戦です。
応急処置的に“使い捨てカイロ”や“蒸しタオル”を肩に当てるという方法がありますが、本気でケアするなら、バスタブにしっかり浸かる“浴槽浴”がおすすめ(肩こりに効く入浴法はこちら)。浴槽浴がすごいのは、15~20分ほどお湯に浸かるだけで、温熱・水圧・浮力という3つの作用が同時に得られること。つまり、カラダが芯から温まるだけでなく、水圧や浮力によって筋肉が自然にゆるまって血行が促され、さらに入浴中に軽いストレッチをするとで、さらに“こり”が取れやすくなるというから何ともお得!
また、固まった筋肉をマッサージでゆるめたり、アロマトリートメントなどでカラダの巡りを高めながら精神的にリラックスすることも、肩こりケアには非常に有効です。ちなみに、大相撲初場所で初優勝し、“日本出身力士として10年ぶりの優勝”と話題沸騰の琴奨菊は、大のアロママッサージ好きだとか。サロンに通うだけでなく、自身もエッセンシャルオイルやアロマキャンドルを数十種類所有し、気分に応じて香りを選んでいるそうです。勝負時に力をフルに発揮するためにも、心身のリラックスタイムは肝心なのかもしれませんね。

一定の負荷がかかったとき、筋肉は自らを守るためにギュッと縮みますが、それが自然にゆるむことはないといいます。肩こりは、いってみれば「ゆるめてくれ~」「動かしてくれ~」というカラダからのメッセージ。だから、意識してゆるめてあげることが肝心で、筋肉がほぐれて“巡り”のよい状態になれば、疲れにくい(疲労物質が溜まりにくい)カラダにもなるということです。
「指が入らないほど肩がカチカチ!」「すっかり肩こりが染みついている」という“肩コリスト”の方も、「昔はこんなことなかったのに…」と、肩こりデビューに戸惑っている方も、さぁ今日から、「動いて、ほぐして、温めて」、“こり”に負けないしなやかなカラダを手に入れましょう!