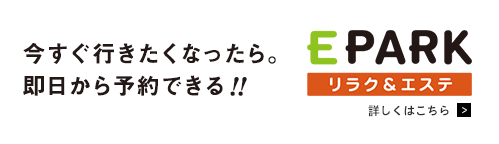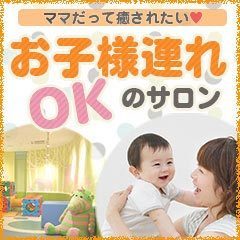2016年1月13日 更新
【肩こりレッスン2】どうして肩はこるの?

誰も教えてくれなかった、“こり”と“痛み”のメカニズム!
“こり”とは、筋肉が張ってかたくなること------。
肩こりレッスン1で、こりの状態をこのようにお伝えしました。では、なぜ筋肉が張ってかたくなると、痛みや重だるさといった、いわゆる肩こり時のような不快感を覚えるのだろう?
ということで、今回はまず“こり”と“痛み”のメカニズムについて探っていきます。
私たちのカラダに張り巡らされている筋肉は、適度に動かすことで収縮と弛緩を繰り返して、“しなやかさ”を保っています。また、この収縮&弛緩がもたらすポンプ作用”によって、老廃物を回収した静脈血を心臓へ押し戻すのも、筋肉の大事な役目なのです。
しかし、何らかの理由で筋肉が“収縮”した状態が続くと、どうなるでしょう?
筋肉のポンプ作用が充分に機能しないため、本来外に運び出されるべき老廃物がそこに蓄積され、筋肉がパンパン張ってかたくなる。これが、いわゆる“こり”の状態。さらに老廃物は発痛物質でもあるので、溜まった老廃物が筋肉内の神経を刺激して、痛みや不快感を引き起こすことに。
これが“こり”と“痛み”のメカニズムだといわれています。
しかし、数ある筋肉の中でも、なぜ圧倒的に肩の筋肉がこってしまうのか?
日本人の8割以上を悩ませる、“こり界”のメジャーリーガー「肩こり」の根源的な原因っていったい何…? さらに追求してまいります。
肩がこるのは人間だけ!?肩こりの3大原因はこれだ!

筋肉の継続的な“収縮状態”が、“こり”と“痛み”を招くことを前章で説明しました。では、私たちの生活の中で、筋肉が“収縮”を続けるのって、どんなときでしょう?
これがすなわち肩こりの根源的な原因となるわけですが、病気によって二次的に起こる肩こりを除くと、肩こりの主な原因としては以下の3つが挙げられます。

「肩がこるのは、人間だけ」「肩こりは、二足歩行を始めた人類に課せられた宿命」などといわれます。確かに動物園に行っても、肩こりに悩んでいそうなライオンやゾウは見当たりません。今からおよそ400万年前、四足歩行から二本の足を使って直立歩行するようになった人間は、手を自由に使うことができるようになったのと引き換えに、肩・腰・ひざなどに多大な負担を強いられることになったのです。
具体的にいえば、私たちはカラダのてっぺんにボーリング玉ほどの重さの頭を掲げ、体重の8分の1ほどの腕をぶら下げた状態で、日々バランスを取りながら活動をしています。この重たい頭や腕を最前線で支えているのが肩や首であり、これらにかかる負担は計り知れません。
もっとも、うまくカラダのバランスがとれていれば、局部的に過度な負荷がかかることはないのですが、デスクワークやスマホ操作、クルマの運転などで長時間前かがみになったり、寝ながら本を読むなど不自然な姿勢を続けると、頭や腕を支える肩や首など特定の筋肉に負荷がかかり、その部分の筋肉が緊張(収縮)して、こりを招いてしまうのです。
ただ座っているだけ=カラダが楽だと思いがちですが、実は動いているときよりも、じっとしている方が筋肉への負担は大きく、とくに“悪い姿勢”を続けることは肩こりのもっとも大きな原因と考えられています。
神経質、緊張しやすい人は要注意!

続いて肩こりの原因その2、老化・運動不足について。
肩こりに悩む小学生がいないように(近年は肩こりも低年齢化しているようですが)、肩こりは一種の“老化現象”ともいえます。それは、年を重ねると筋肉が萎縮して血流悪化→肩こりへと発展しやすいからです。また、筋肉は適度に動かすことでしなやかさを保っているので、筋肉を使わない=“運動不足”も肩こりを招く原因に。
なお、人前でスピーチをするときなど、気づくとカラダがガチガチになっていることってありませんか? 緊張・ストレス・寒さなどで“肩に力が入った”状態が続くのも、筋肉を収縮させて肩をこらせる原因に。これが肩こりの原因その3です。神経質だったり緊張しやすい人は、日常的に肩に力が入りやすいので、必然的に肩こりのリスクも高まると考えられます。
このように、私たちの周りには肩こりを招く要素であふれかえっており、人類の宿命ともいわれる肩こりとうまくつきあうことは、毎日をイキイキと暮らすための大きなヒントにもなりそうです。ということで、次回の【肩こりレッスン】では、肩こりの予防と対処法についてお伝えします!