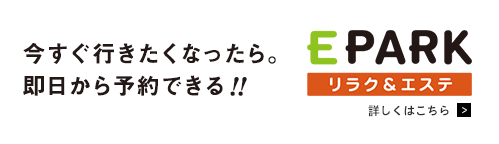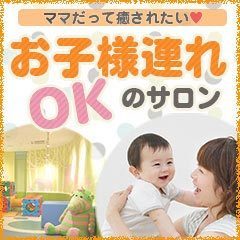2016年12月14日 更新
はじめての鍼★3分でわかる『プチ鍼レッスン』

鍼は珍味に似ている。最初の一歩は勇気がいるが、いざトライしてその奥深い魅力を知ると、なくてはならない存在となる。
東京・池袋の人気サロン、リフレッシュプロさんによると数ある施術コースの中で、もっともリピーターが多いのが「鍼」なのだそうだ。
ある資料によると、日本の総人口に占める鍼灸の受療率はおよそ6~7%(平成25年現在)だという。つまり日本人の9割以上が鍼未経験者という計算になるが、大半の成人は鍼に無関心というよりも、「やってみたいけど怖い」「特別な治療のために受けるもの」といった認識をもっているのではないだろうか?
日本では一部の疾患に対して健康保険も適用される鍼。その一方で、肩こりや疲労回復、冷え、食欲不振など、病院に行くほどではない慢性的な不調にも高い効果が期待でき、さらに近年は、美肌やダイエットを目的とする鍼も注目されている。
そこで今回は、「興味はあるけど、正直どういうものかよく分からない」と、鍼に二の足を踏んでいる方たちのために、3分でわかる“鍼のイロハ”をお伝えしたいと思う。
「ぶっちゃけ、鍼って痛いの?」

「鍼、打ったことある?」と聞かれて、「ないない!えっ、あるの~?」と大げさに手を振りながら答える人は、ほぼ間違いなく、全身に注射針のようなものを刺されることを想像している。
なわけないじゃん!である。ちなみに注射針の太さが約0.7~0.9㎜なのに対し、鍼灸に使われる鍼は0.14~0.34㎜と3分の1ほど。注射針は液体を注入するため中が空洞で先端が尖っているが、空洞が不要な鍼は細くて先端は丸みを帯びている。よって刺入時にチクッとした感覚はあるものの、基本的に痛みはほとんどない。
とはいえ、痛みの感じ方は人それぞれ。痛みに弱い人や子供用に、刺さない鍼(接触鍼)というものもあるので、気になる人は鍼灸サロンで尋ねてみよう。

一般的に使われる鍼は、大人の髪の毛ほどの細さ。長さは30~80㎜程度。

これが刺さない鍼のひとつ、「てい鍼(しん)」。皮膚に接触させるだけでも鍼の効果が期待できるという。
なお、施術に使用する鍼だが、感染症予防のため、現在ほとんどのサロンでエチレンオキサイド滅菌の上、1本ずつ梱包されたステンレス製の使い捨て鍼(ディスポーザブル)を使用。一度使った鍼はその都度廃棄されるため、衛生面に関しても安心だ。
で、鍼は一体何に効くのか?
東洋医学がベースとなっている鍼灸だが、近年はWHO(世界保健機関)やNIH(米国国立衛生研究所)もその効果に着目しており、2010年にはUNESCOが「伝統中国医学としての鍼灸」を、無形文化遺産に指定している。以下はWHOが有効性を認めた疾患だ。
●運動器系……関節炎、リウマチ、肩こり、五十肩、腰痛、腱鞘炎、むちうち、捻挫など
●神経系……頭痛、めまい、神経痛、自律神経失調症など
●循環器系……動悸、息切れ、高血圧症、低血圧症、動脈硬化など
●呼吸器・消化器系……喘息、気管支炎、便秘、下痢、胃炎など
●代謝内分泌系……貧血、通風、糖尿病など
●婦人科系・泌尿器系……生理痛、月経不順、更年期障害、冷え性、膀胱炎、腎炎など
●耳鼻咽喉科系・眼科系……中耳炎、耳鳴り、メニエール病、鼻炎、咽頭炎、眼精疲労など
●小児科系……小児喘息、夜尿症、消化不良、食欲不振など
ところで、なぜ鍼を刺すだけでこれだけの効果が期待できるのだろう?
ここに東洋医学の神秘が隠されている。
東洋医学とは、人のカラダをパーツではなくトータルでとらえ、カラダ全体のバランスを整えることで、本来私たちのカラダに備わっている自然治癒力を高めていくというもの。この考えに基づき、経絡や人のカラダに361あるといわれる経穴(ツボ)にピンポイントで刺激を与えることで、気や血液の流れを整えてカラダを健やかな状態に戻していくのが鍼という施術だ。
具体的には、脈診、腹診、舌診などでカラダの状態を把握したのち、ツボに触れながら必要な箇所に鍼を刺入。これにより痛みの抑制、内臓機能のバランス回復、筋肉のコリやハリの改善、美肌など、さまざまな効果が期待できる。
ちなみに前出のリフレッシュプロさんでは、「リラクゼーションでは物足りない」「もう少し本格的に肩コリをケアしたい」といった方に鍼をすすめているという。
とくに初めての場合、施術前のドキドキが大きい分、施術後の爽快感も格別。ある意味、鍼は非常に達成感のある施術ともいえる。

日本で主流となっているのが、鍼管(しんかん)と呼ばれる管に鍼を入れ、鍼の頭を軽く叩いて刺入する方法。痛みが少なく、確実性が高いとされている。
鍼の施術には国家資格が必要
日本において、鍼を生業として行うことができるのは、医師および国家資格である「はり師」の免許をもつ者である。つまり、鍼の施術者は大学や専門学校で解剖学、病理学、生理学などの基礎医学を学び、鍼の専門的な技術を習得した上で「はり師」の国家試験をパスした人。鍼について分からないことがあれば、遠慮せずに何でも聞いてみるとよいだろう。
なお、鍼を控えた方がいいといわれるのは、発熱時、飲酒時、極度に疲れているときなど。また施術の途中で具合が悪くなったら、すみやかに先生に告げよう。
「終わったあと、すごくものがよく見えるようになるの。景色が違うんだよ」という友人の言葉にぐっと来て、数年前に鍼デビューした自分は、施術後の見事な脱力ぶりに感激し、以来鍼は月イチの恒例行事となった。
私の場合、打つ場所によっては稲妻が走ったようにビビビッと来ることがあり(これを『鍼のヒビキ』というらしい)、「うわー、何ですかこのツボ」「腎臓ですね、少し弱ってます」などと、自分のカラダを媒介に先生と会話をするのもまた楽し。さらに、あちこちに鍼を打たれ、じっと天井を見上げて寝ている自分に、「わしはアゲハ蝶か!」とツッコミを入れるのも悪くない。

刺した鍼に微弱な低周波パルス通電をすることで、筋肉の血行促進などを図る「パルス鍼」。皮膚表面から刺激を与えるもみほぐしなどに対し、深部にある筋肉のこりや緊張に直接アプローチすることができるのも鍼の魅力。
今から2000年以上前に古代中国で発祥し、飛鳥時代(592~710年)に日本に伝わったといわれる鍼は、いまやハリウッドセレブにまで愛されるワールドワイドな存在となり、アンチエイジングを目指す女子たちはこぞって顏に鍼を打っている。
肩こりがおさまらない、食欲がない、生理痛がつらい、美肌がほしい……。わずか0.2mmほどのスレンダー・ボディで、私たちのさまざまなニーズをどっしりと受け止めてくれる鍼は、美と健康維持の強い味方だ。この深遠なる鍼ワールドを知らずに過ごしてきた人たちよ、もう食わず嫌いしている場合じゃないのである。