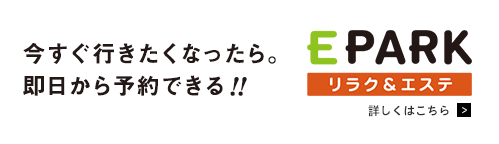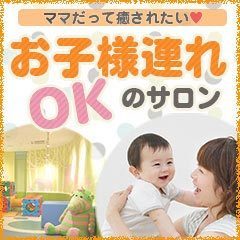2016年4月27日 更新
清潔・迅速・加熱!食中毒から身を守る6つのポイントとは?

食中毒は「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則でしっかり予防
食中毒を予防するには、まず菌をつけないこと。特に、まな板やふきんなどの調理器具を清潔にすることが基本です。そして、調理したものはすぐに食べるようにすること。菌は、時間とともにどんどん増殖していきます。さらに、75度で1分以上を目安に、中まで充分に加熱しましょう。食中毒の多くは梅雨や夏場に多く見られますが、ウイルス性の場合は冬場でも活発です。食中毒にならないために、まずは自分で取り組める予防と対策を行いましょう。
■食中毒はなぜ起こるのか
食中毒は、たとえ食材が傷んでいるなどの問題がなくても、菌が混入したり付着したりしていれば簡単に起きてしまいます。症状は腹痛や下痢、嘔吐が一般的。ただし重症になると、命にかかわることもあります。そんな食中毒の主な原因は、大きく分けて以下の4つです。
<細菌性>
食材に菌が混入することで発生します。主な菌は以下の通りです。
・サルモネラ菌
特に食中毒の発生率が高い菌で、卵や鶏肉に多く見られます。
・O-157(腸管出血性大腸菌)
牛の大腸に生息しており、ベロ毒素を生成します。生の牛肉から検出されるため、焼き肉の際には焼く前と焼いた後の菜箸は別にするのが基本です。
・ウェルシュ菌
集団食中毒を起こしやすく、人や動物の腸管、また土壌にも生息しています。
・黄色ブドウ球菌
加熱しても死滅しない菌として知られています。菌が増殖するときに毒素を作るのが特徴です。
<ウイルス性>
少量でも感染しやすく、冬場でも活発に活動するのが特徴です。
・ノロウイルス
ウイルス性の毒素で食中毒の半数近くを占めています。
・腸炎ビブリオ
貝や魚などの海産物に多い菌です。
<自然毒>
フグやキノコなどの動物性、植物性の毒のこと。
<化学物質>
ヒ素やシアン化合物、メタノールなど。
■食中毒予防と対策のポイント
食中毒の予防の3原則は「つけない」「増やさない」「やっつける」。これは、厚生労働省でも提唱しています。これをもとに、6つの予防と対策のポイントを見ていきましょう。
1)食品の購入
生鮮食品は、できるだけ新鮮なものを選びましょう。消費期限を確認し、肉や魚のドリップが出ていないものを選び、ビニールに入れて持ち帰ります。
2)食品の保存
表記に従って冷蔵や冷凍を行います。冷蔵庫は詰め込み過ぎると、設定温度より高くなっていることがあるので注意しましょう。
3)食品の下準備
まずは、キッチンを清潔にします。肉や魚を触った後は手だけではなく、包丁やまな板もしっかりと洗いましょう。特に生で食べるサラダ類は、肉や魚を切ったものと分けるのがおすすめです。また、冷凍していた肉や魚を解凍したら、菌が増えないように放置せずすぐに調理してください。
4)調理
食品は中まで充分に加熱します。菌を殺すには、中心部を75度で1分以上加熱することが大切です。
5)食事
食事の前には、必ず手をしっかりと洗います。調理したらなるべく早く食べることが肝心です。
6)食べ残し
作った食事を後で食べる場合には、必ず清潔な容器に移し替えて保存しましょう。時間が経ちすぎたものは、思い切って捨てる覚悟も必要です。温め直す際は75度以上で1分、味噌汁などは沸騰させましょう。
◆執筆:青島 幹子
関連キーワード